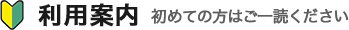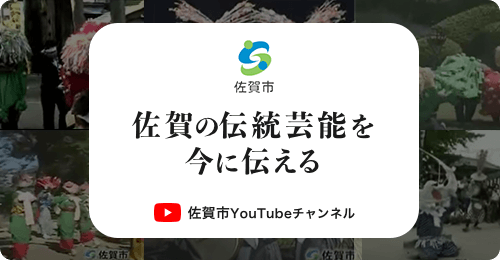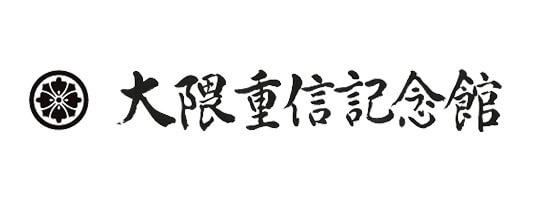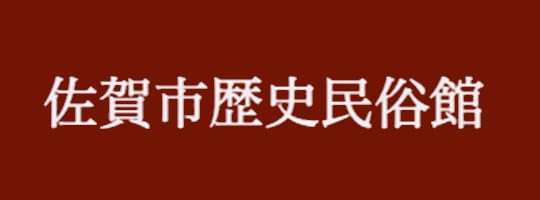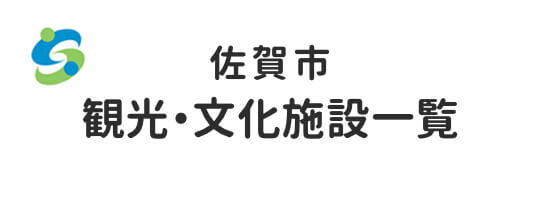ピックアップアーカイブ pickup
-

道祖神社
祭神は、猿田彦神で交通神として知られています。与賀神社の末社で、与賀神社参道のこの地に古くから鎮座されていたと伝えられています。 この社は、1964年(昭和39年)道祖神1400年祭を施行した古い歴史をもっています。
-

循誘小学校
循誘小学校の誕生は、明治8年教正小学校という名前で紺屋町に創立されたのが始まりで、明治17年循誘公民館西隣りの長徳寺南側に当時の予算3,000円で柳町校舎が建設され、明治19年1月21日移転して開校された。学校敷地は、当時思案橋で酒造業をしていた下村辰右衛門(後に国会議員となった)が寄付したものであり、また、佐賀市仲仕組所が500円を寄付した。循誘小学校百周年記念事業が、昭和50年に盛大に実施されたがその記念誌には、この柳町校舎で学んだ人達の思い出が掲載されている。明治44年6月1日、この柳町校舎も老朽化し、狭隘となったので巨勢村に移転。その頃は校舎も新しく、校地も広く佐賀県一小学校といわれていた。小学校の門は佐賀市高木町にあるので小学校の住所は高木町となっている。また、同年それまで勧興校区だった呉服町、千代町、新馬場、馬責馬場、通り小路等が循誘校区に変更された。大正14年には創立50周年の記念式典が挙行され、その記念として校門から南の佐賀劇場手前までの直線道路が通学道路として完成した。このときに架けられた橋に『記念橋』とか『循誘橋』の名前が付けられた。昭和10年5月国鉄佐賀線が開通し、初めての汽車が通るとき、循誘小学校の子どもたちは、線路に沿って日の丸の旗を振って祝ったといわれている。この汽車は通常ガソリンカーと呼んでいて汽車の発車する時の汽笛が『ポーッ』とでなくラッパを鳴らすように『プウッー』と鳴らしていたのが印象深い。この佐賀線は、三国線とも呼ばれていて肥前、筑後、肥後を結ぶ予定で熊本の南関町まで開通する予定であった。児童の数は、創立時は118人であったのが大正10年以来常に1千人を超えていて、昭和35年には最高の34学級の1,750人を記録した。これは戦後のベビーブームが一度に押し寄せたもので、急激な児童数の増加に伴い、どこの市町村でも教室の建設に追われ苦労の時代が続いたようである。この当時佐賀県では大町小学校で3千人を超えた記録があり1学級50人から60人位で教壇のすぐ側まで机を並べていたことも珍しくなかった。しかし近年は子どもの出生率も低下し、児童数も激減している。